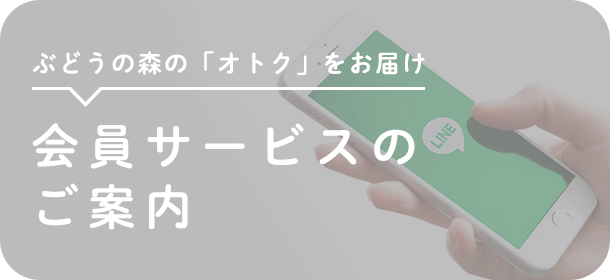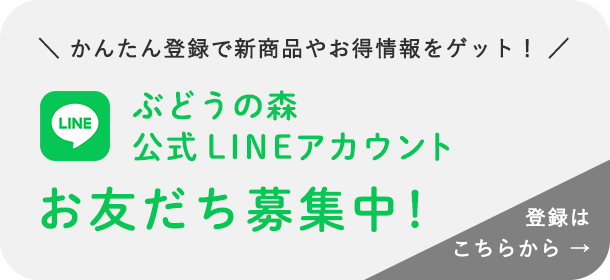ニュース&トピックス
お知らせ
ぶどうの森・本店
[ブドウ園もと・直売所]本年の営業終了のご挨拶
2025.10.15
秋の気配が日ごとに深まり、そろそろ半袖を片付けはじめる2025年の10月中旬。
おかげさまで「ブドウ園もと」は今シーズンも無事に営業を終えました。

2025年7月16日から10月15日正午までの営業期間、悪天候の日もありましたが、幸いなことに一日も休むことなくお客様をお迎えできたこと、そして今年も遠方からも含め本当にたくさんのお客様にご来店いただけたことに、この場を借りて心よりお礼を申し上げます。
農園責任者の白井氏と本未樹さんのインタビューをもとに、広報担当者が今シーズンを振り返りつつ次のシーズンに向けての思いをつづりました。
●2025年のトピック
天候と実り
気候変動の波は世界の農業を脅かしていますが、「ぶどう園もと」も例外ではありません。7月は日照りが続き農業用水の確保が心配される厳しい状況があったかと思えば、8月上旬には線状降水帯が発生し、大雨に見舞われました。(広報担当の私自身、朝出勤した際に水没しているぶどう畑を見たときの衝撃と、「もうだめかもしれない」という絶望的な思いは、今でも鮮明に思い出します。)
それでも、白井氏は天候に恵まれた2025年だったといいます。


たしかに振り返ってみると、世界中の農家の方々が甚大な苦労をされている中で、最終的に「ぶどう園もと」は大きな被害はなく、ぶどうの出来もまずまずという結果でシーズンを終えることができました。そう思うと彼の「天候に恵まれた」の言葉には、日々ぶどうと向き合いながら手入れし続け、自然の力に感謝する謙虚な気持ちが現れたものだと改めて感じるのでした。
収穫時期
酷暑のため、全体的に収穫が前倒しになりました。例年7月の店頭はほぼデラウエア一択であったように思いますが、今年は7月25日頃からニューヨークマスカット、安芸クイーン、アーリースチューベンなどのお馴染み品種もお目見えし、7月末日には10種類を超える品種が店頭を彩りました。

しかしそのおかげでいつもなら9月いっぱい活躍する品種たちも足早に過ぎ去り、名残のシーズンが早くに訪れてしまった感は否めません。おそらくそれは来年以降も続くでしょう。
温かな「人とのつながり」
ブドウ園もとのスタッフは、農業者としてのプライドと技術をもって栽培にあたっていますが、作り手だけで完結するものではありません。そこにはいつも温かく見守り支えてくださる「人とのつながり」があり、本未樹さんによれば、今年も常連のお客様に支えられたシーズンであったと言います。
7月の開店直後、店頭では「久しぶり」「元気だった?」といった声が飛び交う「同窓会」のような雰囲気に包まれ、ぶどうの成長を毎年楽しみにしてくださる常連のお客様との再会を喜びました。そしてシーズン終盤、「そろそろ終わり」とご案内すると名残惜しんで何度も足を運んでくださるお客様の笑顔と温かい言葉がありました。
特に印象的だったのは、大雨の被害を心配してわざわざ声をかけてくださったり、スタッフを気遣って手土産までいただいたりしたこと。お客様からの思いが大きな支えとなったと話します。
また広報担当としては、地元企業である清菓室町さんが、当園のぶどうを使って美味しい「ぶどう餅」を作ってくださったことも、地域とのつながりを感じる大きな喜びでした。わたしたちのぶどうを高く評価いただき、生産者に真摯な対応をもって、素晴らしいお菓子に変えてくださったことに心から感謝いたします。

●次のシーズンとその先の未来に向けて
国産ぶどうを取り巻く市場環境は今、大きな転換期を迎えています。 近年、高級品種「シャインマスカット」人気に牽引され活気に溢れたぶどう市場でしたが、シャインマスカットは作付面積の増加とともに供給過多となり、品質が不安定なものや規格外品も多く出回りはじめました。輸入品種も増加し、すでに高価格を維持できなくなってきており、動向は不透明です。
原点回帰
そんな中で、白井氏が語ったのは、次の時代を見据えた「原点回帰」です。
戦後の日本を支えた巨峰やデラウエアといった伝統品種は、色を付けるための高度な技術が必要であり、栽培が難しい品種。しかし、白井氏は「これまで培ってきた高いぶどう栽培技術をもって、あえてこれらの『価値ある伝統品種』に改めて向き合うつもりだ」と語りました。日本のぶどう栽培の歴史と食文化に貢献すること、そして自然とぶどうと向き合う丁寧な栽培姿勢を貫くこととは、「本物の品質」を生み出すという農業者としての意思の現われでしょう。

また文化醸成のためにも、もっとぶどうを親しんでもらいたいと言います。振り返れば今年からご用意した「ラッピング袋」は1~2房を小さな袋でご用意したものですが、ささやかなプレゼント用に喜ばれました。また複数の品種の粒を混ぜ合わせて袋に入れた「バラエティパック」も、品種の食べ比べができると好評をいただきました。果実離れが進んでいると言われる近年ですが、これからも「ブドウ園もと」ならではの新しい形で果実のある暮らしを提案していきたいと思っています。
種まきと人財育成
もうひとつ白井氏が言及したのが、新事業の種まきと人材育成です。
次の時代に向けた「種まき」として、ぶどう品種の作付けの傍ら、新しい仲間いちじく(無花果)の栽培にも注力していく予定で、すでに7品種の苗木を購入済みとのこと。これまでもいちじくは敷地内で栽培していましたが、苗木が成長して実をつければ種類と収量が増えて、ぶどうの森の新しい秋の顔となるでしょう。今年で7シーズン目を迎える苺とともに、季節を通して多様な「実り」を届けてくれそうです。


さらに、「人財育成」も重要な柱だと言います。
幸いにも白井氏の右腕として、優秀な山﨑さんが次世代を担うリーダーとして力を発揮していますが、ひと昔のような「職人」を育てるのは難しい時代。だからこそ、スタッフ一人ひとりの個性やライフスタイル、キャリアプランに合わせ、「それぞれの働き方に合わせた成長のステージ」を用意することが、ブドウ園もとの成長に不可欠です。
そのための軸として考えているのが「加工品の強化」です。
ぶどうも無花果(いちじく)も、苗木から高品質な生食の果実を安定して出荷できる成木になるまでには数年を要しますし、天候により生食としての品質基準に満たない果実はどうしても生まれてしまいます。
そこで、これらの規格外品を無駄にすることなく、ジャムやジュースなどの加工品に変える取り組みをブドウ園もとでも強化し、これを農園スタッフも企画・製造・販売まで携わっていくことをイメージしています。
単にフードロスを削減するだけでなく、農業技術に加え、商品開発、マーケティング、販売戦略といった多様なスキルを身につける機会を創出します。

今いるスタッフの多様な能力や、これから来てくれる新しい人材の力をいかんなく発揮してもらうために、農園の視点からこの「加工」という付加価値創造の場を提供する。職人としてぶどう栽培の技術を極めたい人、企画者として新しい商品を生み出したい人、広報として農園の魅力を発信したい人、それぞれの情熱が形になる場所を提供することこそ、ぶどう園もとが取り組むべき未来への投資だと考えているのです。
最後に(編集後記)
シーズンの終わりにインタビューをさせていただくようになって3年目になりますが、先を見据えた回答に今年も勉強させていただいたと感じました。
彼らが目指すのは、気候変動や人々の食習慣など大きく変わりゆく環境の中で、農業を担うものとして時代に合わせたアプローチをすること。言い換えると、変わらない大切なことを実現するために、恐れずに変わっていくことかと思いました。分野は違えど、それは私たちひとりひとりにも求められることでしょう。
それにしても、無花果(いちじく)の苗木をすでに購入していたことには驚きました。店頭にならぶのは数年先になりそうなので、また経過報告はこのブログ記事でさせていただこうと思います。
最後になりましたが、今シーズンもブドウ園もとをご愛顧いただきありがとうございます。
これから農園スタッフは冬支度の準備に入り、ぶどう棚の景色も変わっていきますが、どうか季節を通してぶどうの森をお楽しみいただきますよう心よりお願い申し上げます。